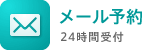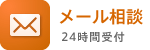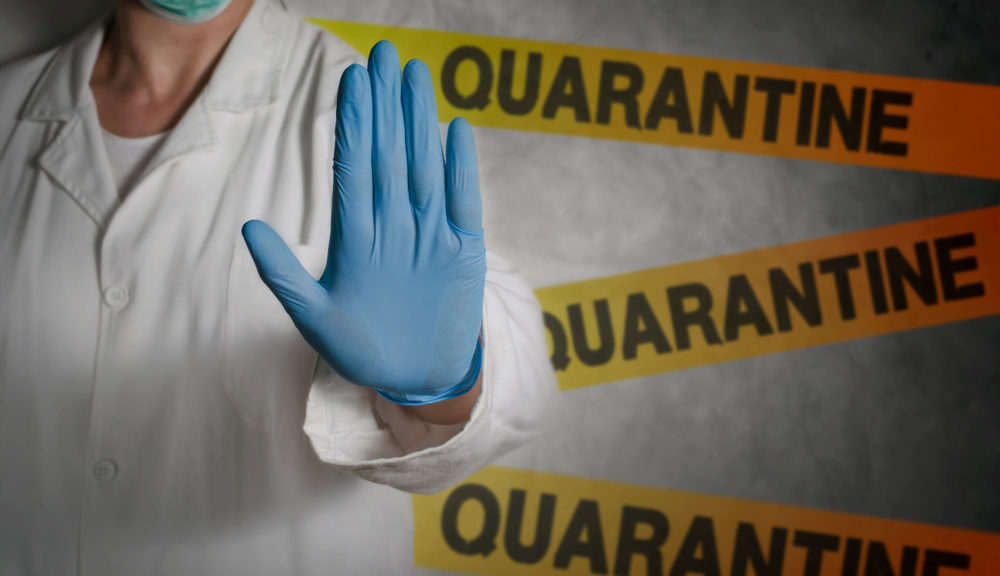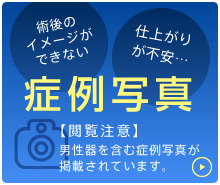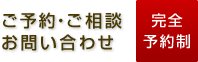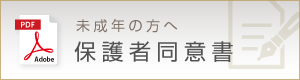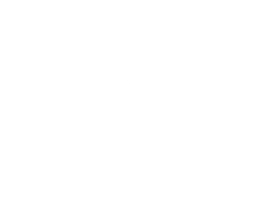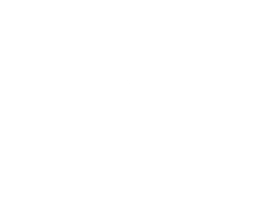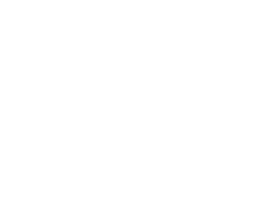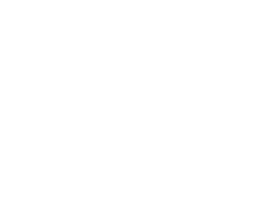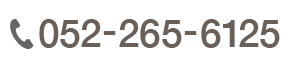性病で男性不妊や未来の赤ちゃんにも影響が!?

性病の中には自覚症状が乏しいものがあり、発見が遅くなってしまうことがあります。
しかし、性病の中には男女ともに不妊を引き起こしたり、妊娠中や出産時に赤ちゃんに感染して流産や早産、赤ちゃんに障害をもたらしたりするものもあります。
ですから、性病はあなた自身や、パートナーの体の問題だけではないのです。
今回は性病が不妊や赤ちゃんに及ぼす影響について紹介します。
もしこの記事を読んで不安を感じたら、栄セントラルクリニックに相談や受診することをおすすめします。
↑↑ 栄セントラルクリニック 性病・性感染症のページ ↑↑
どうして性病が男性不妊を引き起こすのか
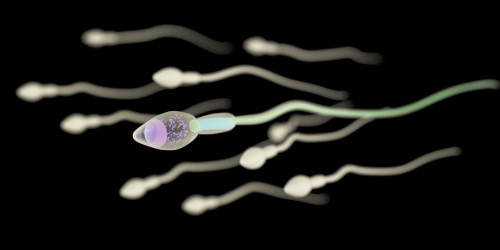
不妊症は、子供を望んで性生活を送っているにも関わらず、1年以上子供を授からない状態を言います。
日本産婦人科学会のホームページによると、不妊に悩むカップルの割合は次のように紹介されています。
不妊のカップルは約10組に1組と言われていますが、近年、妊娠を考える年齢が上昇していることもあり、この割合はもっと高いとも言われています。</引用>
http://www.jsog.or.jp/modules/diseases/index.php?content_id=15より
不妊の原因の約半数は男性にあり、男性由来の原因はさらに次の4つに分類されます。
①造成機能障害(精子をつくることに障害がある)
②精子の通過経路障害(精子の通り道が塞がっている)
③性機能障害(勃起や射精障害)
④性器の内部の炎症によるものこのうち、性病が関係する不妊の原因は②精子の通過経路障害と④性器の内部の炎症によるものです。
精子の通過経路障害とは
精子は精巣で作られるというのは知られているかと思います。
しかし、精巣で作られてから射精に至るまでは次のような経過をたどります。
①約2か月かけ、精巣で精子が作られる
②精子は精巣から精巣上体へ移動し、成熟する
③精子は精巣上体からさらに精管へ移動し、さらなる成熟と射精までの貯蔵を行う
④精管は途中で尿道と合流し、射精に至る
精子の通過経路障害とは、この一連の流れのうち、どこかで詰まりが生じてしまうことをいいます。
詰まりが生じると、射精をしても精子は体外へ出ることができないため、男性不妊になってしまうのです。
性病の中には、感染後、尿道から侵入し、精管を奥へ奥へと進行していくものもいます。
侵入した部位で炎症を起こすと、その部位で詰まりが生じることがあるのです。
性器の内部の炎症によるものとは
精子の通過経路障害で紹介したように、性病は体の内部で炎症を引き起こすことがあります。
精液は通常、精子が活動しやすい状態に保たれているのですが、炎症が生じると精子の運動率が低下し、妊娠しにくい状態になります。
どうして性病が流産、早産を引き起こすのか
男性が性病に感染していることに気づかずにセックスをすると、女性に性病をうつしてしまいます。
女性が性病に感染していることに気づかずに妊娠し放置しておくと、性病の細菌が膣から子宮の内部へ進行します。
子宮内部へと進行した性病は、赤ちゃんと羊水を包む卵膜という組織に感染します。
卵膜での炎症によって、流産や早産に至るケースがあります。
流産は赤ちゃんを授かったという喜ばしい状況から、一気にどん底へと落ちる、非常に辛い経験です。
早産では赤ちゃんが未熟なまま生まれてきたり、細菌に感染したりしているので、後遺症や合併症をもって生まれてくることが多くなります。
さらに低体重で生まれた赤ちゃんは将来高血圧、2型糖尿病、腎臓の病気などを発症するリスクが高まるということも最近ではわかってきています。
性病が赤ちゃんに感染するとどうなるのか

お母さんが妊娠中~出産後に性病に感染していると、赤ちゃんにその性病がうつる可能性があります。
お母さんから赤ちゃんへの感染は、次の3つのいずれかによって起こります。
①胎内感染(赤ちゃんがお腹の中にいる時に感染する)
②分娩時感染(出産時に産道にいる性病に赤ちゃんが触れることで感染する)
③授乳時感染(母乳に含まれる性病を赤ちゃんが口にすることで感染する)
お母さんから赤ちゃんへと感染する性病はたくさんの種類があり、病気によって赤ちゃんに現れる症状も異なりますが、B型肝炎やC型肝炎、HIVも母子感染を起こす性病に含まれます。
B型肝炎やC型肝炎のウイルスに感染して生まれた赤ちゃんが生後間もなく肝炎を発症するということは稀ですが、将来的に肝炎から肝硬変、眼象嵌を発症する可能性があります。
一方、HIVは生まれて間もなくエイズを発症する赤ちゃんもいます。
性病は早期発見が大事

ここまで紹介したように、性病はあなた自身の体だけでなく、パートナーの女性や将来の赤ちゃんにまで悪影響を及ぼします。
さらに性病は治さずに放置しておくと重症化し、治りにくくなったり、体の中で癒着や閉塞を起こして不妊を招いたりします。
感染自体は薬の服用で治すことができますが、一度起こった癒着や閉塞は手術などの外科的な処置を受けなければ完全に回復することはできません。
ですから、性病は可能な限り早く発見し、早く治療を開始することが大切なのです。
さらに自分自身がいくら治療を受けても、パートナーが治療を受けていなければ、何度でも再感染を引き起こします。
ですから、パートナーと同時に治療を受けることが大切です。
栄セントラルクリニックは性病の検査や治療にも対応

性病はカップル間で知らぬ間に感染させ合うことももちろん怖い病気ですが、感染を放置することで不妊や流産・早産、赤ちゃんへの障害をもたらすという点でも怖い病気です。
このような重大な症状をもたらす一方、飲み薬や点滴で治療できるものが多いので悪化する前になるべく早めに受診することが大切です。
栄セントラルクリニックでは次の性病の診療を行っています。
・淋菌
・クラミジア
・梅毒
・HIV
・C型肝炎
・B型肝炎
・ヒトパピローマウイルス HPV
・カンジダ
・トリコモナス
ヘルペスウイルス 淋菌やクラミジアは男性不妊や流産・早産を引き起こす可能性のある性病です。
最近国内で増加傾向の梅毒は、赤ちゃんの脳や肝臓に障害をもたらし、難聴を引き起こすこともあります。
他の性病も、赤ちゃんに感染することによって障害を起こす可能性が高いです。
栄セントラルクリニックではこれらの性病の検査に加え、一部の性病の治療にも対応しています。
さらに、精液検査にも対応しており、精子数や精子の運動率も調べることが出来ます。
「男性不妊の可能性があるのではないか…」と心配されている方は、性病検査と精液検査を同時に行うことも可能です。
栄セントラルクリニックは栄から徒歩5分というアクセスしやすい場所にあります。
診療は深夜0時まで対応しているので、仕事帰りやお出かけのついでの通院も可能です。
土曜・日曜・祝日も診察を行っているため、平日の受診が難しい方でも受診しやすくなっています。
性病は一度で治りきらない方もいますので、通いやすさはクリニック選びの重要なポイントです。
また、いきなり受診するのは抵抗がある場合は、電話やメール、LINEでの相談も受け付けています。
医療機関ではあれよあれよと検査や治療が始まってしまうこともありますが、これらの手段で事前に検査や治療について詳しく相談することで、納得して検査や治療を受けることができるのではないでしょうか。
来院時も医師やカウンセラーは男性が対応し、他の患者さんに会わないように配慮していますので相談しやすい環境を整えるよう努めています。
性病を怖いと思って何もしない間に病状は進行しているかもしれません。
1人で悩まず、まずは相談してみてくださいね。